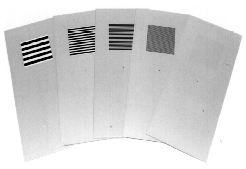
図1 Teller Acuity Cards
肢体不自由養護学校に在籍する重度重複の児童生徒の中には、見えているのかどうかはっきりしない場合が少なくない。本来、動作が制限されている肢体不自由の子供たちにとって、見ることはとても大切な積極的な活動である。どのように見えているのかを配慮して活動を展開したり、見え方に応じて効果的な教材提示をしたり、見やすさを向上させる補助具(レンズやサングラス等)を紹介することは少なかったように思う。
著者の奥山は、東京都立村山養護学校に勤務していた当時、視覚的なケアの必要性を感じながらも具体的な配慮に苦慮していたときに、共同発表者の中野が主催している疑似体験セミナーに参加した。疑似体験を経験してみて、重度重複障害の子供たちへの支援において、視覚的な側面からのアプローチが必要なことを痛感した。また、教育実践を行うにあたり、このような視点を学部全体で共有する必要性を感じた。そこで、東京都立村山養護学校小低部(小学部の低学年)研究会の研究テーマとして実践を行った。本体験セッションでは、東京都立村山養護学校で始めた実践の成果とその後の取り組みを紹介しながら、疑似体験を実施し、視覚障害のある重複障害の人達への支援について考える。なお、本報告は、1998年度東京都教育奨励研究報告書を修正・加筆したものである。
肢体不自由養護学校では、脳性まひ児の半数以上に何らかの視覚障害があると考えられていたり、脳障害のある児童・生徒についても医師の所見の中に視覚障害の存在が示されていることが多い。
しかし、言語的なやりとりや指さしができない児童・生徒に対しては、通常の視力検査を実施することが困難であることから、児童・生徒の視力がどれだけあるのか、どのような見え方をしているのかがわからないケースが多い。そのために、児童・生徒の「見る」ことのニーズに十分に対応することができていないというのが現状であろう。
そこで、障害児の視覚の評価と支援に関する専門家の指導のもとで児童・生徒の「みる」こと(視機能)を評価し支援する方法を学ぶことによって、児童・生徒にとって見やすい環境を工夫していくとともに、見ることを通して授業の中で児童・生徒の主体性を引き出し、コミュニケーションを充実させていくこととした。本実践では、以下のような方法で視機能評価方法の学習・実習・実践とその結果に基づく環境整備を実施した。
(1) ロービジョン(弱視)シミュレーションメガネを使った疑似体験を通して、子どもたちの見える世界の一端を知る。
(2) コミュニケーション支援についての学習会を行う。
(3) 視機能の評価と支援に関する学習会を行う。
(4) 個々の事例の検討を通して、視機能の評価と支援に関する知識を深め、授業の中に生かす。
以下、疑似体験の成果を中心に報告する。
子ども達は毎日の活動をどのように感じているのであろうか。子ども達の視線で世界を見、子ども達の行動を理解し、子ども達がより快適に、より楽しく日々の活動を行えるように心がける必要がある。そのための一つの方法論として、子ども達の世界を彼らの視点(見え方/見えにくさ)で様々な活動を行ってみることを通して想像し、日々の教育実践を振り返るきっかけとする。
視覚に問題を持つ子どもたちが毎日の活動をどのように感じているのか、子どもたちの視点(見え方、見えにくさ)に立って、摂食、あそび、移動の三つの場面を体験した。シミュレーションには、高田眼鏡製のシミュレーショントライアルセットの最重度白濁と視野狭窄3度の2種類を用いた。実習は2人1組で行い、一人は体験者(ロービジョン役)で、もう一人は授業や生活の中でいつも子ども達と接しているように、話しかけたり介助をしたりする介助(教師)役とした。体験者役と介助者役の両方の役割を交替しつつ行った。なお、介助者の役割は、安全確保だけではなく、体験者がどのような行動を取るかを観察することも含まれている。体験者も介助者も疑似体験終了後に感想を記録した。一つの実習を終えたら、すぐに、見え方や感じたことをこのインストラクション・ペーパーにメモして、役割を交代した。なお、体験前に、疑似体験の意義や限界について確認を行い、以下のポイントを意識しながら体験を実施した。
(1) ポイント1 ロービジョンの見え方の多様性を知る
ロービジョンの見え方/見えにくさは、像のボヤケ、グレア光に対する感度の低下(白濁はその中の1つ)、求心性視野狭窄、中心暗点の4つに分類される(小田・中野)。子ども達の見え方/見えにくさの多様性は、この4つの見え方/見えにくさの程度と組み合わせがそれぞれ異なるからだと考えられている。今回の疑似体験では、これらロービジョンの見え方/見えにくさを高田眼鏡製のシミュレーショントライアルセットを用いて体験する。
(2) ポイント2 ロービジョンのディスアビリティは課題によって異なることを知る
視力が低かったり、視野が狭かったりすると何もかもが出来なくなってしまうわけではない。課題によっては、それほど困難を感じないものもある。これは、何を行うかによって必要となる視力や視野が異なるからである。ここでは、食事場面と移動・遊び場面を体験するが、課題によって困難さが異なることを共感的に理解する。なお、以下の点に特に留意しながら体験を行う。
a) 同じ見え方でも容易に達成できる課題とそうでないものがあることを確認する。
b) 視力を要求する課題と視野を要求する課題があることを確認する。例えば、視力が良くても視野が狭いと探索が困難になることを確認する。
c) 体験を分析し、どのような配慮が必要かを考える。
(3) ポイント3 見え方に応じてエイドの工夫や視環境の配慮の仕方が異なることを知る
いかなるタイプのロービジョンにも対応できる見やすい環境というものを設定するのは容易ではない。なぜなら、ロービジョンのタイプによって見えにくさの内容も原因も異なるからである。例えば、一般に部屋の照明は明るい方がよいとされているが、まぶしさを訴えるロービジョンにとっては部屋の照明が明るすぎるのはよくない。このように、見え方に応じて適切な環境条件は異なることに注意しながら体験を行う。
(1) 実習1 食事場面
a) 介助を受けながら食事をしましょう。
2人1組のペアになります。ロービジョン役は手を自由に動かせません。教師役の食事介助を受けながら食事をします。
[ポイント]
b) 自分で食事をしましょう。
器に入った食物を食べましょう。
[ポイント]
(2) 実習2 移動と遊びの場面
2人1組のペアになります。弱視児役は以下の3つの条件で行います。
a) あおむけに横になりながら
b) ハイハイしながら
c) 散歩
a)とb)の条件では、室内でいつも子ども達としている遊び(ボール投げ、紙芝居、パソコンなど)をしましょう。c)では屋外へ一緒に散歩にでかけましょう。
[ポイント]
体験者の主な感想を以下に示す。
(1) 摂食の場面
介助を受けて食べさせてもらう場面では、白濁でも視野狭窄でも、スプーンに載せて示された食べ物がよく見えないことが指摘された。そのために、何の前触れもなくスプーンを口に入れられる場合には強い抵抗感を感じ、逆に、食べ物に関して言語的な説明があったり、口に入れる前にしばらく唇に触れておいてもらうと大きな安心感を得られることがわかった。
自分で食べる場面では、白濁では食べ物が何であるかを見て判断することは難しいが、色を手がかりにして食べ物の場所を見つけることができることがあった。背景とのコントラストが重要であり、例えば、銀色のお盆の上のパンは見えないが、黒いお盆の上のパンは小さなかけらまで見てつまむことができることがわかった。視野狭窄でも色が手がかりになった。距離感がつかめないために食べる動作がぎこちなくなることがわかった。
(2) あそびの場面
白濁では、天井の蛍光灯が非常にまぶしく感じた。光源を背に立った人の表情等はとらえることが難しくシルエットになって見えた。黒いものと影の区別がつかないなど、コントラストのはっきりしないものを見分けることは難しいことがわかった。
視野狭窄では、ものや人の姿が突然視野に入ってくるのが恐かった。距離感や方向感覚がつかめなかったが、相手の黄色い服の色が手がかりになった。
(3) 移動の場面
白濁も視野狭窄も、車椅子に乗って押してもらって移動する場面では、周囲のものとの距離感がわからないために、壁などに接近したりスピードが出ると恐いことがわかった。
疑似体験ではあるが児童のおかれている困難さを経験できたことに大きな意義を感じた。配慮が必要な点を具体的に知ることができたことによって、日常の学習活動等において、児童・生徒の「見えやすい」環境を用意することが出来た。また、何よりも「相手の気持ちを思いやる」きっかけを得ることができたと考える。以下、各場面ごとに気づいたことを列挙する。
(1) 摂食の場面
肢体不自由養護学校の児童・生徒の多くが「食べさせて」もらっている。そして、摂食の場面は重要なコミュニケーションの機会であると考えられている。私たちは摂食指導の研修等で一方的に食べさせることが好ましくないことを知識として耳にしていたが、それが相手にどういう気持ちにさせるのか体験するとができた。疑似体験を境に摂食に関する配慮を更に深めることができた。
摂食時の配慮で最も重要なのは、これから何を口に入れるのかを知らせることであった。そのためには、第一に、視覚的にとらえやすいようにスプーンの運びを工夫したり、光源の位置を工夫してスプーンと背景とのコントラストを高めることが必要である。第二に、スプーンにどんなものがのっているのかを言葉で説明することが必要である。食べ物の名前を説明するだけではなく、味や固さ、温度についても説明することが必要である。第三に、口の中へスプーンを運ぶ前に、口唇の感覚や味覚で食べ物を確かめるための配慮が必要である。口唇でスプーンを止めると食べ物を確かめるための時間的な余裕が生まれる。その結果、もし食べたくないものであれば口が動かないかもしれない。児童・生徒とのコミュニケーションが成功するきっかけも得られる可能性がある。
また、視覚的にとらえやすいように食べ物と背景(食器やお盆)とのコントラストを高める工夫をすることによって「食べさせてもらう」ことから「自分で食べる」ことを支援できる可能性があることを学んだ。
(2) あそびの場面
私たちはあそびや学習のやりとりの中で、繰り返し繰り返しおもちゃや教材等を児童・生徒に見せるということを行っている。しかし、児童・生徒が提示したものに興味を示さないということも日常的に経験している。その場合、興味を示さない理由を明らかにすることができずに「集中できない」等という評価をしてしまうことも少なくない。
今回の疑似体験を通して、摂食と同様に、見せたいものに対する光源の位置や、見せたいものと背景とのコントラスト等について私たちが留意しなければ、何が提示されているのか全く見えないことがわかった。今までにも何かを見せるときに背景に衝立を置くことがあったが、それは見せたいもの以外を隠すという配慮にとどまっていた。疑似体験を境にして、衝立を利用する場合にも「光源」と「コントラスト」という要素まで徐々に配慮するようになり、児童・生徒にとってより見やすい環境を用意するようになってきている。
(3) 移動の場面
私たちは今まで、校内で何気なく児童・生徒の車椅子を押してきた。しかし、周囲の状況がよく見えないためにスピードが出ると怖いことがわかった。摂食の場面と同様に、車椅子を押すスピードについて配慮をしたり、言語的に説明するなどを配慮が必要であることを学ぶことができた。
疑似体験により、視機能に応じて視環境の整備を行う必要性が認識されたが、担当している児童・生徒の見え方がわからなければ、体験の成果を実践に結びつけることが困難である。従来、ランドルト環を用いた視力検査か、動物の図版等を用いた萬国式視力検査に言語的に応答したり指さしで応答できる児童だけが視力検査の対象となっていた。しかし、言語的な応答が難しいケースも少なくない。そこで、行動観察による視機能評価を実施した。
行動観察、特に、乳幼児の視力検査用に開発されたTAC(Teller Acuity Cards)を用いて、視力等の評価を実施した。そして、児童の「見え方」「見えにくさ」に基づいて、児童がより見やすい環境を配慮し、児童とのやりとりを深める実践を実施した。
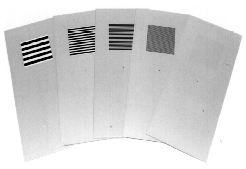
図1 Teller Acuity Cards
小低部の児童30名の中で、身体計測の視力検査(ランドルト環か萬国式)の対象になっていたのは6名のみで、この6名の児童に関してはいずれも言語的な明確なやりとりが可能であった。しかし、残りの24名はこれまで視力検査が実施できなかった。
今回TACを利用して視力評価を試みたところ、新たに8名の視機能が明らかになった。TACでは、縞模様が印刷された横長のカードを児童・生徒の提示して、その時の視線の動きを見るという「やりとり」を通して視機能を評価する。言語的なやりとりが難しい児童・生徒の場合は、カードの方へ注意を喚起するというやりとりの工夫が必要である。やりとりの工夫を試みることによって、今後も更に多くの児童・生徒の視機能を評価することができる可能性がある。
TACという新たな評価方法を知ることができた意義は大きい。肢体不自由養護学校には言語的なやりとりが難しい児童・生徒が数多く在籍しており、彼らの「感じる世界」の一端を知る方法を得たことによって、相手の気持ちを思いやり、相手の立場に立つことを考えるきっかけを得ることができたと考えている。
(1) A児の事例
A児に音の出るおもちゃを提示して、わずかながらに反応が感じられることや、音楽に対して嬉しそうな表情が見られること等が担任から報告された。また、認知的に初期の児童の「見る」ことをどのように考えればよいのかという質問が出された。
これに対してアドバイザーから以下のような評価や提案を受けた。見ることだけが独立するのではなく、楽しいことと一緒に見ることがあるのが望ましい。A児にとって最もわかりやすいことを見つけることが大切である。先々には、見ることが何かの予告になると面白い。また、目を動かすことが何かのサインになる可能性もある。違う色のものを提示して選ぶという活動をする場合、視覚の発達で考えると明暗、色、形の順でわかるようになるので、色の違いの他に明るさの違いを明確にする必要がある。二つのものをコピー機にかけてみると明るさの違いを簡単に調べることができる。視覚的な違いの他に多様な感覚の違いがあるとなおわかりやすい。
A児の事例を通して、見ることだけを単独で扱うのではなく、多様な感覚と一緒に用いて楽しくなるように工夫することが重要であることを知った。また、視覚的な違いとして、色の差よりも明るさの差が重要であることを知ることができた。私たちが日常的に用いている教材にも、色の他に明るさや手触りなど工夫の余地がたくさんあることがわかった。
(2) B児の事例
B児にペープサートを提示しながら話しかけると目が動いて笑顔が出るが、話しかけないと笑顔が出ないことや、音声刺激なしで光あそびをしている時のこと等が担任から報告された。また、どの程度見えているのかわからないという疑問が出された。
これに対してアドバイザーから以下のような評価や提案を受けた。見るときに音声の刺激や触覚の刺激などいろいろな感覚を提示した方が楽しいし、見る動機が生まれやすい。それに見えるかもしれないということをあきらめないで見やすいものを提示することが大切である。今までの情報からどの程度見えているのかはまだわかりにくいが、光あそびの光の強さに関しては、視力が非常に低い場合には強い光でないとわからないことがあるが、ある程度視力を持っている場合には強い光は不快なので、光の強さに対する配慮や直接光を目に当てないような工夫が必要である。眼疾患で視神経萎縮と診断されている場合には、視野の障害、特に視線を向けているところが見えない中心暗点が起こってくる可能性が高い。この場合、視線を向けるとよく見えないので、ものを提示すると「見る」ために視線をそらす様子が見られることを理解する必要がある。だから中心暗点のある子どもにTACを実施すると、必ずしま模様と反対側を見ることになる。B児の場合もペープサートを提示したときに片方に目が寄っている様子が見られたので、視線をはずして見ているかもしれない。また、ペープサートを動かしたときにあるところで目を大きく動かした様子が見られたが、B児の見える部分からペープサートがはずれたので目を動かした可能性がある。
B児の事例を通して、「視神経萎縮」と診断されている場合には中心暗点が起こってくる可能性が高いことと、中心暗点の見え方の特徴を知ることができた。B児の他に視神経萎縮と診断されている児童は3名いることが明らかになるとともに(30名中計4名)、その他にも視線をそらして見ている児童がいることが明らかになった。中心暗点の特徴を知らなければ、「興味がない」とか「見ない」と判断される可能性があり、視機能の評価の知識の重要性を痛感した。
(3) C児の事例
C児は呼名に対して答えたり、くすぐりあそびで予期して笑ったり等といろいろなやりとりが可能であることや、光あそびのときに光(行灯)の方を向くことがあること等が担任から報告された。また、視力が「明暗程度」という場合、光の見え方に段階があるのかという質問が出された。
この質問に対してアドバイザーから以下のような評価や提案を受けた。光の見え方の段階というのは重要な要素で、光の明るさを変えていきながらどのくらいの明るさの時に気づくかということを「輝度計」で調べることができる。この変化を見ることは子どもの生活の質を考える上でとても大切なことかもしれない。C児は未熟児網膜症という診断を受けているが、眼科医に血管新生がどの程度あるのかということと網膜の状態を聞いて欲しい。毛細血管が新生して網膜がはがれていると暗点が生じて見えない部分がある可能性がある。また、血管の新生が多いと白内障と同様に明るさがないと見えないが明るすぎるとまぶしいという状態になる可能性がある。行灯の光がC児に近づくと必ず頭を落と様子が見られるので、C児はまぶしさを感じているのではないか。網膜の中心部に色がわかる細胞があるので、網膜の状態がわかると色の識別ができる可能性があるかどうかがわかる。さかさまつげがあると角膜が傷ついてまぶしさが生じるので、手術することを勧める。
C児の事例を通して、未熟児網膜症やさかさまつげでどのような見え方の障害を生じる可能性があるのかを知ることができた。また、適切な明るさを明らかにして提示するためには「輝度計」を利用して測定することが丁寧で有効な方法であることを知った。
(4) D児の事例
D児に対して絵画語彙発達検査を試みたところ、最初の練習問題でも指さしも視線も定まらなかったので、同じ内容の設問を実物を用いて行ったところ答えることができたということや、絵画語彙発達検査の図版をB5からA4に拡大して、特徴の強い部分に色づけをしてD児に提示したところ、2/3程度を正答することができたということが報告された。また、D児に対してTACを試みた結果、0.07まで確実に反応を得たことが報告された。
上記の質問に対してアドバイザーから以下のような評価や提案を受けた。絵画語彙発達検査の図版を拡大して色を付けたことが適切であった。視力障害がある子どもたちは線画の線そのものが見えない可能性があるので、線を太くして輪郭をはっきりされることが必要であり、TACでどのくらいの線幅が弁別できるのかということが線幅を考えるときの大まかな目安になる。また、実物や写真は、色が淡かったり輪郭がはっきりしていないのでわかりにくい場合が多く、輪郭の線がはっきりした線画の方がわかりやすい。輪郭がわかると形をとらえることができ、色が付いていれば背景とそのものの違いがわかりやすくなる。背景とそのもののコントラストをつけるためには絵を切り取って黒いものの上に置くとよい(黒っぽいものは白い物の上に置く)。D児のものを見分ける力について考えた場合、担任と一緒に黒いボードに白いペンでお絵かきをしながらお話をするというのもよい。
D児の事例を通して、児童・生徒にとって見やすい絵カード等を作るためには、輪郭や色や背景とのコントラストが重要であることを知ることができた。また、もののわかりやすさという点で、従来は「実物→写真→線画→文字」という理解をしていたが、見やすさという点では異なることを知った。
以上の4名の事例の検討を通して、それぞれの眼疾患に関連した機能障害(見え方の問題)と具体的なケアの方法や、見ることの発達に応じた取り組みや教材の配慮や工夫の方法についての知識を深めることができた。
今までは児童・生徒の「見る」ことに関してわからないままにしてあることが多かった。今回の実践を通して、肢体不自由養護学校の児童・生徒に視覚障害を持つ人々と同様のニーズがあることが明らかになったが、今後、研究を終えた後にもこれらのニーズにどのように継続的に応えていくのかということが大きな課題とされた。その後、関係者の努力で、2000年度に東京都肢体不自由教育研究会に視機能支援部会が発足した。なお、東京都肢体不自由教育研究会とは、肢体不自由教育に関わる教員が自主的に運営する研究会組織であり、2001年の段階で、26の専門部会に分かれている。肢体不自由養護学校では視覚障害を併せ持つ指導・生徒が多い。しかし、言語的なやりとりや指さしができない児童・生徒に対しては、通常の視力検査を実施することが困難であるために、どのような見え方をしているのかがわからないケースが多い。そのために、児童・生徒の「見る」ことのニーズに応えることに多くの教員が困難を感じていることが発足のきっかけとなった。視機能支援部会は、毎年5月に総会と春期研究協議会、11月に秋期研究協議会、その他夏期や土曜日の午後などに研修会を開催している。